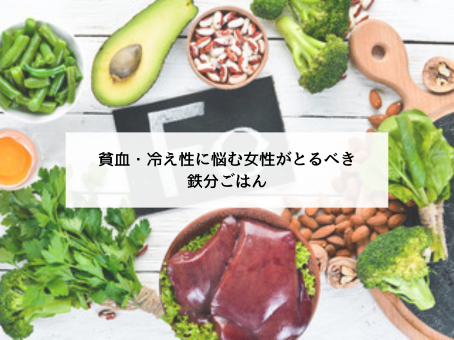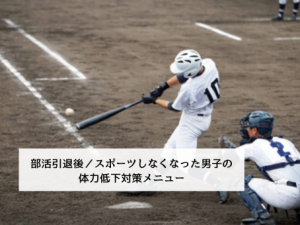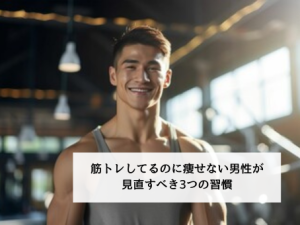BEYOND二子玉川店の石田です!
今回は貧血や冷え性に悩んでいる方向けの記事になっております😁
少しでもみなさんの参考になりますように✨
朝起きるのがつらい、階段を上ると息切れする、手足が常に冷たい、集中力が続かない。
このような症状に悩まされている女性は決して少なくありません。
厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、20-40代女性の約65%が鉄欠乏状態にあり、そのうち約20%は鉄欠乏性貧血を発症しています。
女性の鉄欠乏は、月経による鉄損失、妊娠・授乳期の鉄需要増加、ダイエットによる摂取不足など、複数の要因が重なって生じます。特に現代女性は、1日の鉄推奨摂取量10.5mgに対して、実際の摂取量は平均7.3mgと大幅に不足しており、慢性的な鉄欠乏状態に陥っています。
鉄欠乏による貧血と冷え性は密接に関連しています。鉄は酸素運搬を担うヘモグロビンの構成成分であり、また体温調節に重要な役割を果たします。適切な鉄分摂取により、ヘモグロビン値が1g/dl上昇すると、基礎体温が平均0.3℃上昇することが研究で明らかになっています。重要なのは、単に鉄分を摂取するだけでなく、吸収率を最大化する食べ方を実践することです。
この記事をご覧いただいている方へ。
この記事をご覧いただいている皆さまは、健康面に気を使い、食生活や運動習慣の見直し、フィットネスジムに通われている。もしくは、入会等をご検討されている健康意識の高い方々ではないでしょうか?
実際に、厚生労働省が、健康づくりのための身体活動基準・指針を作成し、生活習慣病予防のための運動を推進しています。
また、日本政策金融公庫が発表した消費者動向調査(令和3年7月)では、運動面や食に関する志向で、“健康志向”の方が多く年々と増加しています。
より皆様が、健康的で充実した人生を歩めるよう、誠意を込めて記事を執筆いたしましたので、どうか最後までご覧ください。
<その他資料>
※スポーツ庁の資料(新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健康状態等に関する調査研究(令和2年度))では、コロナ終息後のパーソナルトレーニングジムの利用者数は急増中。
※経済産業省の『特定サービス産業動態統計速報』の結果でも、フィットネスジム並びに、パーソナルジム利用者は数多くいらっしゃいます。
【PR】BEYOND


BEYONDは全国120店舗以上を展開する、BEST GYM AWARD受賞のパーソナルジム。美ボディコンテストでの入賞者や資格をもつ、プロのパーソナルトレーナーのみが揃っております。
過度な食事制限やトレーニングなく、ライフスタイルに合わせて無理なく継続できます。
コースは大きく以下3つにわかれているため、目的に合ったトレーニングを選択可能です。
| 料金(税込) ※最小プランの場合 | 内容 | おすすめ | |
| ライフプランニングコース | 月々10,100円~ ※281,600円 | パーソナルトレーニング 食事管理 | 初心者の方向け |
| ライフプランニングコース(サプリ付き) | 月々10,600~ ※296,720円 | パーソナルトレーニング 食事管理 サプリメント | 目標がある方向け |
| 回数券コース | 月々4,800円~ ※96,800円 | パーソナルトレーニング ストレッチ | 継続したい方向け |
※当社指定の信販会社を利用した際の分割料金となります。・10回券96,800円の場合:分割回数:24回/支払い期間:24ヶ月/手数料率:年利7.96%/支払い総額:115,850円
特に回数券コースの月々4,800円~は、業界内でも最安値級で良心的です。
BEYONDが気になる方は、まず無料体験トレーニングを活用してみてください。
\今なら入会金50,000円が無料/
鉄欠乏が引き起こす身体への影響


出典:Adobe Stock
鉄欠乏の影響を正しく理解することで、適切な対策の重要性を認識できます。
貧血のメカニズムと症状
ヘモグロビン合成の阻害により、酸素運搬能力が低下します。鉄は赤血球内のヘモグロビンの中心に位置し、酸素分子と結合する役割を担います。鉄が不足すると、ヘモグロビン濃度が低下し、組織への酸素供給が不十分になります。
段階的な鉄欠乏の進行により、症状が徐々に現れます。第1段階では貯蔵鉄(フェリチン)が減少し、第2段階では血清鉄が低下、第3段階でヘモグロビンが減少して鉄欠乏性貧血となります。早期発見と対策により、重篤化を防げます。
酸素不足による全身症状として、疲労感、息切れ、動悸、頭痛、集中力低下などが現れます。これらの症状は日常生活の質を大幅に低下させ、仕事や家事のパフォーマンスに深刻な影響を与えます。
簡単に言うと・・・
鉄が不足するとそれに伴って酸素が不足し、疲労感、息切れ、動悸、頭痛、集中力低下という症状が出るのです💦
冷え性との関連性
熱産生機能の低下により、体温調節能力が損なわれます。鉄は細胞内のミトコンドリアでエネルギー産生に関与し、体熱の生成に重要な役割を果たします。鉄欠乏により、基礎代謝率が10-15%低下し、冷え性が悪化します。
血流循環の悪化により、末梢への熱供給が減少します。貧血により血液の酸素運搬能力が低下すると、心臓は血流量を増やそうとしますが、同時に末梢血管の収縮が起こり、手足の冷えが生じます。
甲状腺機能への影響により、体温調節ホルモンの分泌が低下します。鉄は甲状腺ホルモンの合成に必要であり、鉄欠乏により甲状腺機能が低下し、基礎体温の維持が困難になります。
女性特有のリスク要因
月経による鉄損失が最大のリスク要因です。正常な月経でも1回あたり約15-20mgの鉄が失われ、過多月経の場合はさらに多くの鉄が失われます。月経周期を考慮した鉄分補給が重要です。
妊娠・授乳期の鉄需要増加により、鉄欠乏リスクが急激に高まります。妊娠中は胎児の成長と血液量増加により、通常の2倍以上の鉄が必要となり、授乳期も継続的な鉄供給が求められます。
ダイエットによる摂取不足が現代女性の鉄欠乏を悪化させています。極端な食事制限や肉類の摂取制限により、鉄の摂取量が大幅に減少し、慢性的な鉄欠乏状態に陥りやすくなります。
鉄分の種類と吸収メカニズム


出典:Adobe Stock
効果的な鉄分摂取のためには、鉄の種類と吸収メカニズムを理解することが重要です。
ヘム鉄と非ヘム鉄の違い
ヘム鉄は動物性食品に含まれる鉄で、吸収率が15-35%と高く、他の栄養素の影響を受けにくい特徴があります。肉類、魚類、レバーなどに豊富に含まれ、貧血改善に最も効果的な鉄源です。
非ヘム鉄は植物性食品や鉄強化食品に含まれる鉄で、吸収率は2-20%と変動が大きく、他の栄養素や食品成分の影響を強く受けます。ほうれん草、大豆、ひじきなどに含まれ、適切な食べ合わせにより吸収率を向上させることができます。
吸収効率の最適化により、限られた摂取量でも効果的に鉄を補給できます。ヘム鉄と非ヘム鉄を組み合わせ、吸収促進因子を活用し、阻害因子を避けることで、総合的な鉄吸収率を最大化できます。
鉄吸収に影響する因子
吸収促進因子を積極的に活用することで、鉄の利用効率を向上させます。ビタミンCは非ヘム鉄の吸収を3-4倍に向上させ、動物性タンパク質は鉄の溶解性を高めます。有機酸(クエン酸、リンゴ酸)も鉄の吸収を促進します。
吸収阻害因子を理解し、適切に対処することで、鉄の無駄な損失を防げます。タンニン(茶、コーヒー)、カルシウム、食物繊維、フィチン酸(穀類、豆類)は鉄吸収を阻害するため、摂取タイミングを調整する必要があります。
胃酸の重要性により、鉄の溶解と吸収が左右されます。胃酸分泌が低下すると鉄吸収が著しく低下するため、胃酸分泌を促進する食品(酢、レモン、梅干し)の併用が効果的です。
鉄分豊富な食材と含有量


出典:Adobe Stock
効果的な鉄分補給のために、食材別の鉄含有量と特徴を把握し、日常の食事に取り入れましょう。
| 食材カテゴリー | 代表的食材 | 鉄含有量(100gあたり) | 鉄の種類 |
|---|---|---|---|
| レバー類 | 豚レバー、鶏レバー、牛レバー | 13.0-36.0mg | ヘム鉄 |
| 赤身肉 | 牛もも肉、豚ヒレ肉、羊肉 | 2.0-4.0mg | ヘム鉄 |
| 魚介類 | かつお、まぐろ、あさり、しじみ | 1.9-29.7mg | ヘム鉄 |
| 緑黄色野菜 | ほうれん草、小松菜、春菊 | 2.0-2.8mg | 非ヘム鉄 |
| 豆類・種実類 | 大豆、小豆、ごま、アーモンド | 2.0-9.9mg | 非ヘム鉄 |
| 海藻類 | ひじき、わかめ、のり | 2.0-55.0mg | 非ヘム鉄 |
動物性食品(ヘム鉄源)の活用法
レバー類は最も効率的な鉄源で、豚レバー100gで成人女性の1日鉄推奨量の3倍以上を摂取できます。週1-2回、50g程度の摂取で十分な効果が期待できます。調理時は短時間で火を通し、栄養素の損失を最小限に抑えます。
赤身肉は日常的に摂取しやすく、良質なタンパク質も同時に補給できます。牛もも肉、豚ヒレ肉は脂肪が少なく、鉄含有量も豊富です。1日100-150gの摂取により、必要な鉄分の30-40%を確保できます。
魚介類では、かつおやまぐろなどの赤身魚、あさりやしじみなどの貝類が特に鉄分豊富です。あさりの佃煮やしじみの味噌汁は、日本の伝統的な鉄分補給食品として優秀です。週3-4回の摂取を目標とします。
植物性食品(非ヘム鉄源)の効果的摂取法
緑黄色野菜は鉄分以外にも葉酸、ビタミンC、βカロテンなど、造血に重要な栄養素を含みます。ほうれん草は茹でることで鉄含有量が濃縮され、小松菜は生でも摂取できる利便性があります。1日200-300gの摂取を目標とします。
豆類は植物性タンパク質と鉄分を同時に摂取できる優秀な食材です。大豆製品(豆腐、納豆、味噌)は日常的に摂取しやすく、発酵により栄養価も向上します。1日1-2品目の豆製品摂取を習慣化します。
海藻類では、ひじきが特に鉄含有量が多いですが、近年の分析では従来の数値より低いことが判明しています。それでも重要な鉄源であり、カルシウムや食物繊維も豊富です。週2-3回、小鉢1杯程度の摂取が適量です。
鉄吸収を最大化する食べ合わせ


出典:Adobe Stock
同じ鉄含有量でも、食べ合わせにより吸収率は大きく変わります。科学的根拠に基づいた組み合わせで、効率的に鉄分を補給しましょう。
ビタミンCとの相乗効果
ビタミンCの還元作用により、非ヘム鉄の吸収率が劇的に向上します。ビタミンCは3価の鉄を2価に還元し、腸管での吸収を促進します。鉄1mgに対してビタミンC25-75mgの摂取により、吸収率が3-4倍に向上します。
効果的な組み合わせ例として、ほうれん草のソテーにレモン汁、ひじきの煮物にピーマン、豆腐ハンバーグにトマトソースなどがあります。調理時にビタミンCを添加することで、手軽に吸収率を向上させられます。
ビタミンC豊富な食材を常備し、鉄分食材と組み合わせます。柑橘類、いちご、キウイ、ブロッコリー、パプリカ、じゃがいもなどを活用し、毎食ビタミンCを意識的に摂取します。
動物性タンパク質の促進効果
MPF(Meat Protein Factor)により、植物性鉄の吸収が促進されます。肉、魚、鶏肉に含まれる特定のアミノ酸やペプチドが、非ヘム鉄の溶解性を高め、吸収を促進します。
具体的な組み合わせとして、ひじきと鶏肉の煮物、ほうれん草と豚肉の炒め物、大豆と牛肉の煮込みなどが効果的です。少量の動物性タンパク質でも十分な促進効果が得られます。
ベジタリアンの場合でも、卵や乳製品を摂取できれば、同様の促進効果が期待できます。完全菜食主義の場合は、発酵食品や酸味のある食品を積極的に活用し、鉄吸収を最適化します。
有機酸の活用
クエン酸、リンゴ酸、酢酸などの有機酸は、鉄をキレート化し、吸収しやすい形に変換します。これらの酸は胃酸の分泌も促進し、鉄の溶解を助けます。
実践的な活用法として、酢の物、マリネ、ドレッシングを鉄分食材と組み合わせます。梅干し、レモン汁、酢を調味料として活用し、毎食少量ずつ摂取することで、継続的な吸収促進効果が得られます。
発酵食品も有機酸を豊富に含み、鉄吸収を促進します。味噌、醤油、酢、ヨーグルト、キムチなどを日常的に摂取し、腸内環境の改善と鉄吸収の向上を同時に図ります。
鉄吸収を阻害する食品と対策


出典:Adobe Stock
鉄吸収を阻害する因子を理解し、適切に対処することで、摂取した鉄分を無駄なく活用できます。
タンニンとカフェインの影響
タンニンの阻害メカニズムにより、鉄吸収が大幅に低下します。緑茶、紅茶、コーヒーに含まれるタンニンは、鉄と結合して不溶性の複合体を形成し、吸収を阻害します。食事と同時摂取により、鉄吸収率が50-90%低下します。
適切な摂取タイミングにより、阻害を最小限に抑えます。鉄分豊富な食事の前後1-2時間は、茶類やコーヒーの摂取を避けます。どうしても摂取したい場合は、ミルクを加えることで、タンニンの影響を軽減できます。
代替飲料の活用により、水分補給と鉄吸収を両立させます。麦茶、ルイボスティー、ハーブティー(カモミール、ペパーミント)はタンニン含有量が少なく、食事時の飲み物として適しています。
カルシウムとの相互作用
カルシウムの競合阻害により、鉄の腸管吸収が低下します。カルシウムと鉄は同じトランスポーターを使用するため、高濃度のカルシウム存在下では鉄吸収が阻害されます。
摂取タイミングの調整により、両方の栄養素を効率的に摂取できます。カルシウム豊富な食品(乳製品、小魚、緑黄色野菜)と鉄分食品は、できるだけ別の食事で摂取するか、時間をずらして摂取します。
バランスの取れた摂取により、長期的な栄養バランスを維持します。1日を通して見れば、両方の栄養素を十分に摂取できるよう、食事計画を立てます。完全に避ける必要はなく、適切な配分を心がけます。
食物繊維とフィチン酸の対処法
不溶性食物繊維は鉄と結合し、吸収を阻害する場合があります。しかし、食物繊維は腸内環境改善に重要であり、完全に避けるべきではありません。適量摂取と調理法の工夫により、阻害を最小限に抑えます。
フィチン酸の中和により、穀類や豆類からの鉄吸収を改善できます。浸水、発芽、発酵により、フィチン酸が分解され、鉄の利用性が向上します。玄米は白米より鉄含有量が多いですが、フィチン酸も多いため、適切な処理が重要です。
調理法の工夫により、阻害因子を減らし、促進因子を増やします。酸性条件での調理(トマト煮、酢の物)、発酵食品の併用、ビタミンC添加などにより、総合的な鉄吸収率を向上させます。
実践的な鉄分ごはんレシピ


日常的に作りやすく、鉄分補給効果の高いレシピを、科学的根拠に基づいて紹介します。
朝食:鉄分チャージモーニング
ほうれん草とベーコンのスクランブルエッグ
材料(2人分):ほうれん草100g、ベーコン2枚、卵2個、バター10g、レモン汁小さじ1、塩こしょう適量
作り方:ほうれん草を茹でて水気を切り、ベーコンと炒めます。溶き卵を加えてスクランブルエッグにし、仕上げにレモン汁を加えます。ほうれん草の非ヘム鉄、ベーコンのヘム鉄、レモンのビタミンCが相乗効果を発揮し、朝から効率的に鉄分を補給できます。
鉄分強化シリアルボウル
材料(1人分):鉄分強化シリアル30g、牛乳150ml、いちご5個、キウイ1/2個、アーモンド10粒
作り方:シリアルに牛乳を注ぎ、カットしたフルーツとアーモンドをトッピングします。強化された鉄分とビタミンCが豊富なフルーツの組み合わせにより、手軽に鉄分補給ができます。忙しい朝でも継続しやすいメニューです。
昼食:オフィスでも作れる鉄分ランチ
あさりとトマトのパスタ
材料(2人分):パスタ200g、あさり200g、トマト缶1/2缶、にんにく1片、オリーブオイル大さじ2、白ワイン50ml、パセリ適量
作り方:あさりを白ワインで蒸し、トマトソースと合わせてパスタと絡めます。あさりの豊富なヘム鉄とトマトのビタミンCが効果的に組み合わさり、美味しく鉄分補給ができます。冷凍あさりを使用すれば、手軽に作れます。
ひじきと大豆の五目煮弁当
材料(4人分):ひじき20g、大豆水煮100g、人参50g、油揚げ1枚、だし汁200ml、醤油大さじ2、みりん大さじ1、砂糖小さじ1
作り方:戻したひじきと野菜を炒め、調味料で煮込みます。作り置きができ、お弁当にも最適です。植物性鉄分が豊富で、食物繊維も摂取できる栄養バランスの良いおかずです。
夕食:家族で楽しむ鉄分ディナー
牛肉とピーマンの炒め物
材料(3人分):牛もも薄切り肉200g、ピーマン3個、玉ねぎ1/2個、醤油大さじ2、酒大さじ1、片栗粉小さじ1、ごま油大さじ1
作り方:牛肉に下味をつけ、野菜と一緒に炒めます。牛肉のヘム鉄とピーマンのビタミンCが相乗効果を発揮し、家族全員の鉄分補給に効果的です。短時間調理で栄養素の損失を最小限に抑えます。
レバニラ炒め(マイルド版)
材料(3人分):豚レバー150g、ニラ1束、もやし1袋、牛乳50ml、醤油大さじ2、オイスターソース大さじ1、にんにく1片、生姜1片
作り方:レバーを牛乳で臭みを取り、野菜と炒めます。最強の鉄分食材であるレバーを、家族みんなが食べやすく調理します。週1回の摂取で、大幅な鉄分補給効果が期待できます。
症状別カスタマイズ戦略
個人の症状や生活スタイルに応じて、鉄分補給戦略をカスタマイズすることで、より効果的な改善が期待できます。
重度貧血の集中改善プラン
ヘモグロビン値8g/dl未満の重度貧血では、医師の指導下で積極的な鉄分補給が必要です。1日20-25mgの鉄摂取を目標とし、ヘム鉄を中心とした食事プランを実践します。
具体的な食事プランとして、朝食にレバーペースト、昼食にあさりの味噌汁、夕食に赤身肉のメイン料理を組み込みます。毎食ビタミンCを意識的に摂取し、茶類は食間に限定します。
経過観察と調整により、改善状況を把握します。月1回の血液検査でヘモグロビン値を確認し、改善に応じて食事内容を調整します。目標値達成後も、維持のための継続的な鉄分摂取が重要です。
軽度貧血の予防・改善プラン
ヘモグロビン値10-12g/dlの軽度貧血では、食事改善による自然な回復が期待できます。1日15-18mgの鉄摂取を目標とし、バランスの取れた食事を心がけます。
週単位の食事計画により、無理なく鉄分を補給します。週2回のレバー料理、週3回の赤身魚、毎日の緑黄色野菜摂取を基本とし、季節の食材を活用して飽きのこない食事を実践します。
生活習慣の改善も同時に行い、鉄の利用効率を向上させます。十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理により、造血機能を最適化し、食事からの鉄分を効果的に活用します。
冷え性改善重点プラン
体温上昇効果を重視した食材選択により、鉄分補給と冷え性改善を同時に図ります。生姜、にんにく、唐辛子などの体を温める食材と鉄分食材を組み合わせ、相乗効果を狙います。
温かい料理中心の食事プランにより、内臓から体を温めます。鉄分豊富なスープ、煮込み料理、鍋料理を積極的に取り入れ、冷たい食べ物や飲み物は控えめにします。
血行促進食材の併用により、鉄分の効果を最大化します。ビタミンE(ナッツ類、植物油)、オメガ3脂肪酸(青魚、亜麻仁油)、ポリフェノール(ベリー類、緑茶)を組み合わせ、血流改善を促進します。
継続のための実践的コツ


鉄分ごはんを無理なく継続するための、実践的なコツとシステムを紹介します。
食材の常備と下準備
冷凍食材の活用により、いつでも鉄分料理が作れる環境を整えます。冷凍ほうれん草、冷凍あさり、冷凍レバーなどを常備し、忙しい日でも手軽に鉄分補給ができるようにします。
作り置きおかずにより、毎日の調理負担を軽減します。ひじきの煮物、レバーの甘辛煮、牛肉のしぐれ煮などを週末に作り置きし、平日は温めるだけで鉄分豊富な食事が摂れるようにします。
調味料の工夫により、手軽に鉄分と吸収促進因子を摂取します。レモン汁、酢、トマトケチャップなどを常備し、普段の料理に少量加えることで、鉄吸収率を向上させます。
外食・コンビニでの選択術
外食時のメニュー選択により、外出先でも鉄分補給を継続します。焼き鳥(レバー)、牛丼、あさりの味噌汁、ほうれん草のおひたしなど、鉄分豊富なメニューを優先的に選択します。
コンビニ食品の活用により、手軽に鉄分補給ができます。サラダチキン、ゆで卵、ひじきの煮物、ほうれん草のごま和えなど、鉄分を含む商品を組み合わせて購入します。
飲み物の選択により、鉄吸収を最適化します。外食時は鉄分阻害の少ない麦茶やウーロン茶を選び、ビタミンC入りの飲料があれば積極的に選択します。
効果測定と記録
症状の記録により、改善状況を客観視します。疲労感、息切れ、冷え、集中力などを10段階で評価し、週単位で記録します。食事内容との関連性を分析し、効果的な食材や組み合わせを特定します。
定期的な血液検査により、数値の改善を確認します。3ヶ月に1回程度、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、フェリチン値を測定し、食事療法の効果を客観的に評価します。
食事記録アプリの活用により、鉄分摂取量を可視化します。スマートフォンアプリで食事内容を記録し、1日の鉄分摂取量を把握します。目標達成度を確認し、不足分を翌日以降で調整します。
まとめ:鉄分ごはんで健康的な毎日を
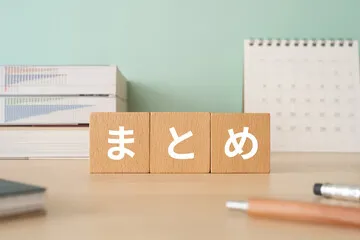
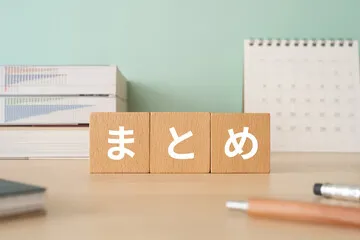
出典:photoAC公式HP
貧血・冷え性に悩む女性にとって、適切な鉄分ごはんは症状改善の鍵となります。重要なのは、単に鉄分を摂取するだけでなく、吸収率を最大化する食べ方を実践することです。
ヘム鉄と非ヘム鉄の特性を理解し、ビタミンCや動物性タンパク質との組み合わせを活用することで、限られた摂取量でも効果的に鉄分を補給できます。また、阻害因子を避け、日常生活に無理なく取り入れられる食事パターンを確立することで、長期的な改善効果を維持できます。
今日から、毎食1品目の鉄分食材を意識的に取り入れてみませんか?😁
小さな変化の積み重ねが、数ヶ月後の大きな体調改善につながります。適切な鉄分ごはんは、貧血や冷え性の改善だけでなく、エネルギーレベルの向上、集中力の回復、免疫力の強化など、多面的な健康効果をもたらし、あなたの生活をより活力に満ちたものにする力を持っています。
科学的根拠に基づいた鉄分ごはんで、健康で美しい毎日を手に入れましょう!
ここまでお読みくださりありがとうございました!
BEYOND二子玉川店からのお知らせ


現在BEYOND 二子玉川店では、通常11,000円の体験トレーニングを現在無料で受け付けております!
ダイエットをしたい方、筋肉増量したい方、今一度フォームを見直したい方、まずはぜひ体験トレーニングにお越しください!
お問い合わせについては、こちらのLINEにて友達ID検索していただくと、無料カウンセリング、体験トレーニングのご予約ができます!
LINE ID: @278rrcmf
※ご登録後、お名前を添えたメッセージをご送信ください!
お問い合わせは、上記LINE@以外にもHPのお問い合わせフォームやお電話にて承っております。
店舗詳細
BEYOND二子玉川店
東京都世田谷区玉川3-6-12 第7明友ビル4F
営業時間 10:00~22:00